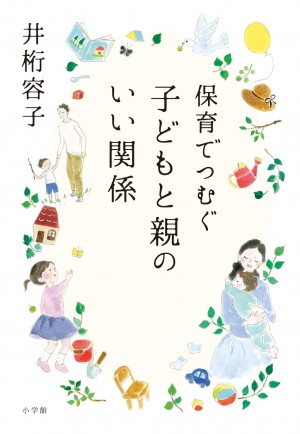お知らせ
2016.3.24
東京家政大学ナースリールーム主任保育者が提案!子育てと共に、親もまた育っていく「友育ち」のために必要なこと! 『保育でつむぐ 子どもと親のいい関係』
この記事は掲載から10か月が経過しています。記事中の発売日、イベント日程等には十分ご注意ください。
「日本の保育や教育の現状は、どの角度から見ても悪化しているように思われて、とても気がかりです。
今、子育てや自分自身の育ちの家庭に悩みをもつ親世代を本当に応援できるのは、保育者しかいないように思うのです。
子どもにとっては人生のスタートの時期に、大人にとっては親としてのスタートの時期に出会い、日々、継続的に、しかも数年間にわたって、ときにはプライバシーにまで踏み込みながら、かかわりをもつことができる保育者こそが、親子の育ちを支えるもっとも身近な存在だと思うのです」
東京家政大学ナースリールームの主任保育者・井桁容子さんは、 現代の子どもと大人の関係を心配し、保育者の重要性をうったえます。さらに「困った子どもが増えたのではなく、困った大人に困らされている子どもが増えて、困った親が増えたのではなく、親になりきれないで困っている親たちがいるのです」と続けます。では、保育者が保護者にできることはなんなのでしょうか?
井桁さんは「登園時間の親子との接触を大事にしよう」と心がけているそうです。なぜなら、朝夕の親子の様子、例えば見られていると気づかないときの母親の表情や口調、子どもの表情やしぐさ、声の調子などから、昨夜、あるいは今朝、その家族に起こったことや、その日の心もちがよく見えてくるので、さりげなく思いを受け止めることが早めにできるから。保護者への対応は、相手から問題を投げかけられる前に、日常の何気ないやりとりのなかに嗅ぎ取って、具体的な場面を通してカバーしておくことが効果的だといいます。
具体的には、
「『うわ~、今日は元気な"おはよう"ですねえ』と声をかければ、『そうなんです。パパが、昨日出張から帰ってきたからうれしいんだよね』と、昨日までとはまるで違った緩やかな笑顔とセットの母親の返事に、ここ数日の母子の表情の硬さは、緊張と疲れからだったのだと理解できます」
著者は本書の中で、子どもが育つように、親もまた育っていく「共育ち」という考えを提案! 保育者が「共育ち」をサポートすれば、子どもの気持ちを理解し、親のイライラが解消され、子育てを楽しむヒントになると伝えます。真の意味での「子育て支援・親支援」とは何か? 本当に子どもが求める大人とはどんな存在なのか? 豊富なエピソードをまじえながら、お母さんや保育者さんたちにやさしく語りかける新しい時代の保育・育児指針です。
著/井桁容子
関連リンク
-

スマホ・喫煙はNG! 高齢出産を避ける!(特に父親) 英語の早期教育は問題! 子どもの「発達障害」を防ぐためにできること。 『発達障害の改善と予防』
-
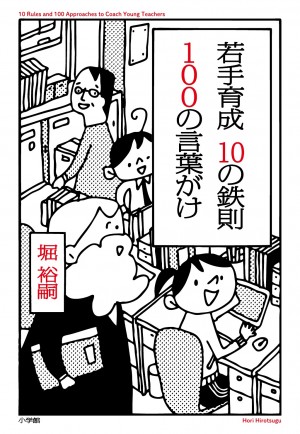
アラフォー以下は、「自律」より「承認」を求めている! 教育のプロが教える『若手育成 10の鉄則 100の言葉がけ』
-

「セックスレスになったカップルは別れます」。出生率2.01、婚外子54.8%、事実婚革命を起こしたフランス人の"愛"と"SEX"と"子育て"の秘密大公開! 『フランス人は「ママより女」』
-
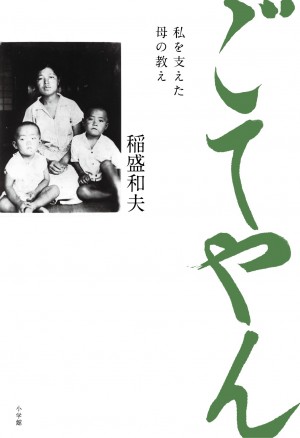
ウチノヨメ。『学校と一緒に安心して子どもを育てる本』の動画をアップしました。
-
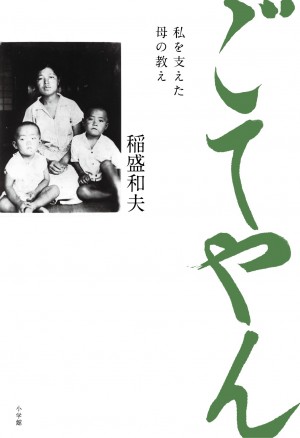
「正しいことを貫く」母の影響から生まれた稲盛和夫の経営哲学。 『ごてやん 私を支えた母の教え』